本日から参院選。
お招き頂いていた8時からの藤田ひかる氏の出陣式に出席。
新聞報道内容では、
主義主張に一票を投じる決め手となる差を感じない、、、
のは個人的感想ですが、
先週の木曜日・金曜日の夕方、NHKの討論番組を見て、
藤田さんがトータル的に一番期待できる、、、という想いを強くしている次第。
5人が立候補しているので、選択肢が多い長野選挙区。
多くの方が関心を持ち、投票に行かれる方が増えることを期待します。
県庁へ行き、向山副委員長と共に
健康福祉部長を訪ねる。
昨日まで行われた委員会では、
正副委員長は進行に注力をする、、、といった向きが強く、
質問などをあまりしないことになっているので、
少し時間を取って貰い意見交換。
委員会での意見も踏まえ、様々な項目をお聞きしました。
- 受診傾向、、、コロナ前に比べて病院へ行かなくなった。施設にいる方は病院へ行かずに施設で療養する傾向もある
- 地域で病床数の増を望まれる声も多いが、病床数を増やして利用率が低いと、財政的に厳しくなる
- 病院の役割分担、、、在宅医療をどう考えるか
- 地域医療構想における許可病床よりも必要数で
- 広島市では4つの病院の統合で1000床の病院ができる
→医療資源の効率的活用 - どういった方が病床を必要とするのか
- 介護施設のようなところのベットも役割分担として認識する必要があるのでは
- 救命救急センター、、、当初は4信に一つ、、、という考え方だったが、南信は、北に諏訪日赤、南に飯田、真ん中に伊那中央、、、となっている。
- 秋田県は8医療圏だったが、今は3医療圏になっている
- 子どもを産めない地域をつくらない(以前の知事発言)
- どのくらいの移動時間まで許容範囲か、、、
→平均として、初産だと10時間以上、経産婦でも3時間ほど、陣痛から出産までにかかることが多いので、正常な分娩ならば。
(助産院も正常分娩が前提ということなので、同様の考え方) - 現状も正常分娩を見込めない場合は、入院しての対応をする
→入院までは必要ないが、不安な方への対応として、木曽地域では来年度からホテルの宿泊補助などを検討している
→その場合、上の子をどうするか
→救急車など、妊婦さんに対応した設備を備える
・・・など、木曽病院でお産ができなくなった場合、「子どもを産めない地域をつくらない」をどう実現するか - 引き続き医師の確保をお願いしながら、不安の解消の研究と実践をお願いしたい
- 医師募集を広く呼び掛けてもあまり意味がない
- ドクターバンク、新幹線の延線は人気。松本も。人が多いところは人気。
→症例、居住環境は大きく影響
→住民の受け入れ姿勢(コンビニ受診が少ないなど)
→就学支援など - こども病院の赤字幅が大きい理由は、少子化も影響
→資料報酬をどう稼ぐか - オンライン診療の現状と課題について
→病院と在宅の役割分担を
→移動診療車、導入・維持費が高額
→オンライン診療は通常の8割程度の診療報酬点 - 現在の医師不足の原因の一つを研修医制度という声があるが、メリット、デメリットを明確にすべき
- 信濃医療福祉センター(南信唯一の医療型障害児入所施設(肢体不自由児・重症心身障害児支援))について
→入所希望者は増えていない
→建設時は県でも補助をした
→建設後40数年で、もっと古い病院などがあるのですぐに建替えは考えていない - 訪問介護について
→県内に514事業所
→職員数も横ばいで、50代以降の職員がほとんど
→全国一律の報酬が中山間地では合わない
→経営改善、人件費やサービス提供の支援(訪問介護の加算率などの利用) - 就労継続支援A型の現状について
→スコアが変わって経営が厳しくなったところはあるが、事業所は大きく減ってはいない(6つ廃業、5つ新規) - 農福連携について
→他に比べても賃金が多く、上手くいっているところが多い
→農家サイドからしても、人手が足りない時に手伝って貰えて良い - 福祉的視点によるCCRC、街(拠点)づくりについて
→以前は都会の高齢者を受け入れて、、、という発想
→今は、多様な人が集まるまちづくりといった視点 - 産後支援のメニューについて(翌日追加)
→母親にとって、様々な支援メニューがあったほうが良いだろう
→もちろんその通りだが、助産師のような国家資格と民間資格では、支援に差があるのが現実
→東京の区では民間資格の事業所にも、家事代行などのサービスにクーポン券(利用補助券)の利用ができるところもある
→実績が積まれれば。
といった意見交換を率直にさせて頂きました。
昼過ぎ、
子どもの学びをトコトン支える県民の会
の第1回会議を傍聴。
冒頭知事より:
人口減少、少子化の中で、将来の日本、長野県を考えた時、子どもたちの学びをどうするか。学校関係者と協議をしているが、子どもたちが学びの主役であり、保護者、地域の方の協力が必要、、、と。
といった資料を元に討議などが行われました。
小学校、低学年の子が家に帰ってこない、、、友達の家に寄っていたが「学校の指導が悪い」
保護者との関係が険悪になることを恐れて、、、保護者の主張を学校が受け止めるしかない現状
中学校、小さなサインを見逃さない、、、と休憩時間も休まず
生徒たちのトラブル、、、生徒間で解決できないことが多く、先生が対応することが多い
小さなケガやトラブルも報告しないと
部活動については、地域移行は進んでいるが、、、まだまだ負担
地域連携はありがたいが、、、
学校評価制度、狙いは改善のためだが、先生は気にする
クレームの類でも気にする
人事異動で新しい赴任地へいくと、
これまでの学校のルール、行事などの前例踏襲、、、
変えるのは難しい
学力と子どもたちの生涯使える力、、、保護者との認識の違い
- 登下校の見守りなどについて
→学校から出れば学校ではない
→学校から出れば、法令上は学校の責任ではない
→学校はやるべきだが、先生がやるべきではない - 学校徴収金の徴収や管理について
→学校行事等で急に欲しいものがあると集めたい時もある
→給食費は、学校でやらなくても良いが、では、誰がやるのか
→学校の事務担当職員の仕事にはなっていない
・・・これこそDXで進めれば良いのでは? - 地域ボランティアについて
→探究などの授業では必要
→草刈りなどは必要ない、、、では、誰がやるのか
→(保護者)学校だけにおんぶにだっこはよくない
→長野県は移住者が多いので風土を知らない人もいる
といった話もあり、、、
昔よりも学校に求められることが多い
クレームは決まった人のことがある
上手く対応できれば良いが、、、
第三者が対応してくれると良い
担うべきこと、、、止めるべきことは止める、、、しかし、それを誰が担うのか?
最後に知事から
先生方の負担を減らすことに異論はない
指導要領などを守ることは法令順守で大切だが、変えることも重要
職員のカスハラ対策もやる必要がある
長野県は学校の現場から、学びの県として意義を
・・・教職員や行政職員は、
どちらかというと批判を受けやすい職種であると感じます。
なので、政治である程度守る、線引きを明確にする、、、
そういったことが必要ではないか、、、感じた次第です。
・・・・・・
夕方は、春から副知事になった新田氏と意見交換。
- データをしっかりと利用して原因分析と予測、それでどうなるか、困るのか?など問題意識を持つこと
- 例えば、医療体制のグランドデザインや農地の地域計画など、見方が変わる
- 例えば、今回の米不足での米の中間業者の利益、林業従事者と木材の最終売値
不都合な未来にしないために!
- 道路が少し窪んで穴が開いていた場合、5分あれば埋めることができるが、そこにタイヤを取られて事故になった場合、現地へ行って調査し、警察を呼んで、保険屋さんも呼んで、、、時間も金もかかる、、、といった意識を持つ
- 飯田や下伊那は、利便性が良くなって都会の企業が進出してくると、更に人手不足が深刻になることを懸念する既存企業もある。しかし、、、AIなどの発達で、そもそも仕事がなくなるかもしれない
- 自動運転が一般になれば、駐車場も必要なくなるだろう、、、中心地の駐車場はどうなる?
・・・多くの情報から、様々な未来を見ている方、、、
そんなことを強く感じると共に、
法律でダメでも、
国へ要望するなど変える情熱を持っている方、、、
であると感じました。
再任された関副知事の安定感と合わせ、
頼もしい布陣になったと思いました。














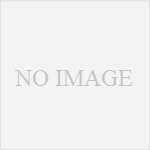

コメント